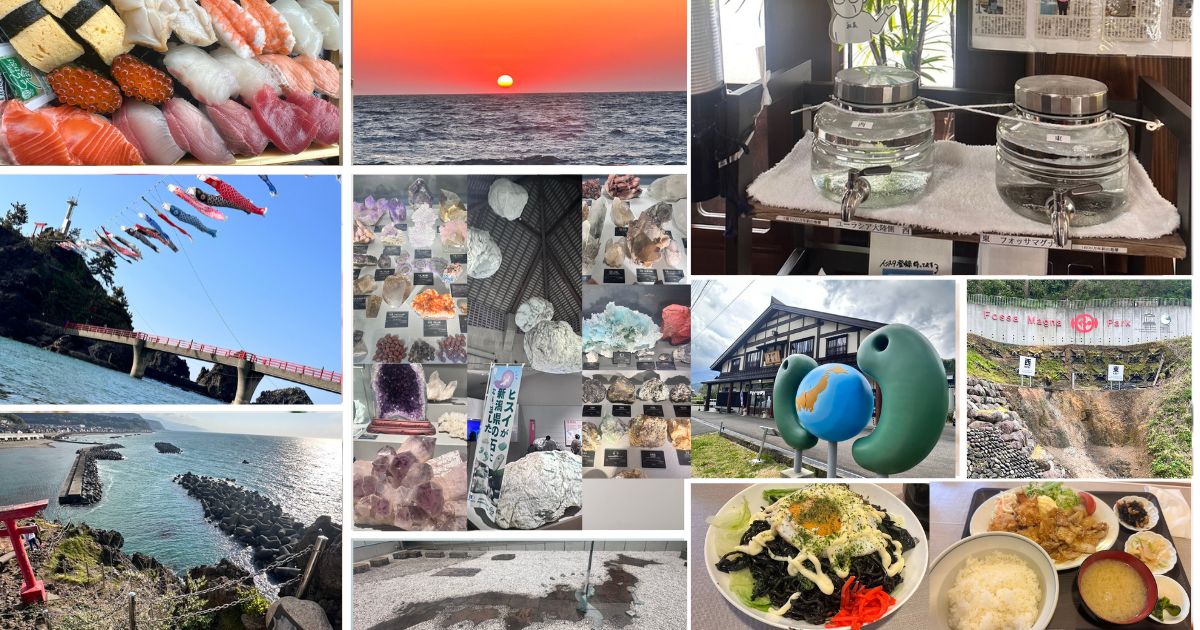「大切なのは、どれだけ多くのことをしたかではなく、どれだけ心をこめて行えたかです。」
― マザー・テレサ忙しさの中で、気づけば「もっと頑張らなきゃ」「成果を出さなきゃ」って思ってしまうこと、ありませんか?
私自身、そんなふうに感じることがよくあります。でも、マザー・テレサのこの言葉に出会ったとき、ふと立ち止まりたくなりました。
“それは、心をこめてできたことだったかな?”
たくさんのことをこなすより、
ひとつひとつに気持ちを添えることのほうが、
ずっと人の心に残るのかもしれません。マザー・テレサの生涯と、”心をこめる”という生き方
マザー・テレサ(1910–1997)
1910年、マザー・テレサは現在の北マケドニアに生まれました。
18歳でアイルランドのロレト修道女会に入り、「テレサ」という修道名を得て、1931年にインドへ。カルカッタの聖マリア学院では、地理と歴史を教える教師として、上流階級の女子教育に携わっていました。
ユーモアのある授業は生徒たちにも人気で、1944年には校長も務めました。けれどその目は、いつも街の片隅にいる貧しい人々に向けられていたのです。
1946年、黙想の旅の途中、彼女は“もっとも貧しい人々の間で働くように”という啓示を受けたと語っています。
スラム街の中へ、自らの足で
1948年、教皇ピウス12世の特別許可を得て、テレサは修道院を離れます。
白いサリーとサンダル姿でスラム街に入り、チョーク1本で始めたのは、路上の子どもたちへの授業でした。やがて教え子たちが彼女のもとに戻り、ボランティアが集まり、寄付が届き始めます。
「神の愛の宣教者会」の設立と“死を待つ人々の家”
1950年、「神の愛の宣教者会」がバチカンに認可されます。
その目的は、「飢えた人、裸の人、家のない人、体の不自由な人、病気の人、必要とされることのないすべての人、愛されていない人、誰からも世話されない人のために働く」こと。テレサはインド政府から譲り受けたヒンドゥー教の廃寺院をホスピスに改修。
「死を待つ人々の家」では、患者の宗教を尊重しながら、最期の時間に寄り添いました。ヒンドゥー教徒にはガンジス川の水を、
イスラム教徒にはクルアーンを読んで。どんな人にも、最後まで「その人らしく」生きてほしい――それがテレサの想いでした。
世界へ広がる“心のケア”
宣教活動はインド全土、やがて南米、アフリカ、欧米へ。
1965年以降は世界規模となり、修道士会や信徒会も次々と誕生します。1979年、ノーベル平和賞を受賞した際も、テレサはこう語りました。
「私のための晩餐会は不要です。その費用を貧しい人々に。」
「このお金で、いくつのパンが買えますか?」
マザー・テレサの生涯と活動
18歳で修道女となり、1931年にインドに赴く。
インド・コルカタで貧困と病に苦しむ人々に出会います。
やがて「神の愛の宣教者会」を設立し、生涯にわたり困難な状況にある人々のために尽くしました。
1952年には「死を待つ人の家」を開設し、
路上で命を落としそうな人々に、尊厳ある最期と、静かな愛を注ぎました。
「この世で最大の不幸は、誰からも必要とされていないと感じることです」
彼女が届けていたのは、物質以上のもの…
「あなたは大切な存在です」という無言のまなざしだったのです。
「心をこめる」とは? ― 本当の意味を考える
「心をこめて」と聞くと、ちょっとむずかしく感じることがあるかもしれません。
でも、それって、意外ととても自然なことなのかもしれません。
たとえば…
誰かのことを思いながら、そっとお茶をいれるとき。
「ありがとう」と名前を呼んで伝えるとき。
ちょっと面倒だなと思いながらも、やっぱり手を伸ばしてあげたいと思ったとき。
そんな何気ない瞬間に、私たちはもう「心をこめる」という行動をしているのかもしれません。
マザー・テレサは、こう語っています。
「愛とは、大きな愛情をもって、小さなことをすること。」
たとえばこんな日常の場面にも、心をそっと添えることができます。
- 忙しい朝でも、笑顔で「いってらっしゃい」と伝える
- 料理を作りながら「おいしいって思ってくれるかな」と思う
- スマホを置いて、相手の目を見て話を聞く
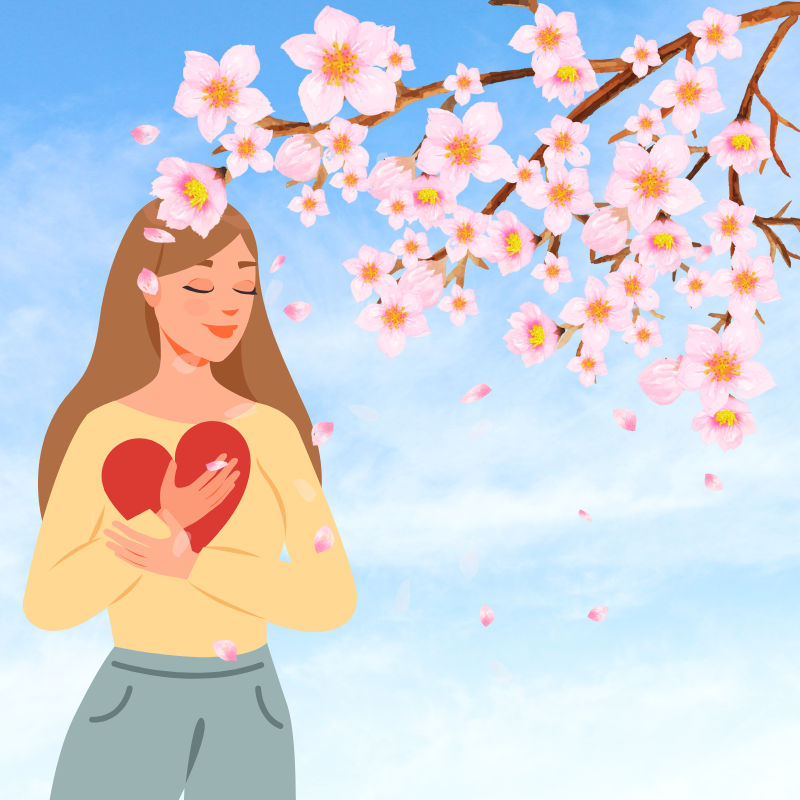
不思議ですよね。
誰かのために心をこめたはずなのに、
気づけば自分の心もそっと満たされていたりする。
「心をこめる」って、誰かを思いやると同時に、
自分にもやさしくなる行動なのかもしれません。
量より、心の深さを ― マザー・テレサの哲学
マザー・テレサの活動は、大きなイベントや華やかな演説ではありませんでした。
ただ、目の前のひとりに向き合うことの連続。
「大きなことはできないかもしれない。でも、小さなことを大きな愛で行うことは、誰にでもできる」
その信念があったからこそ、彼女は世界中の人々の心に響く存在になったのです。
まとめ|心をこめるという選択が、日常を変える

マザー・テレサは、数えきれないほどの人に手を差し伸べました。
けれど彼女の本当のすごさは、たった一人にも全力の愛を注ぎ続けたこと。
私たちの毎日も、そんなふうに変えられるのかもしれません。
たくさんのことはできなくても、
今日という一日に、ひとつでも「心をこめた瞬間」があれば…
それは、きっと小さな奇跡です。